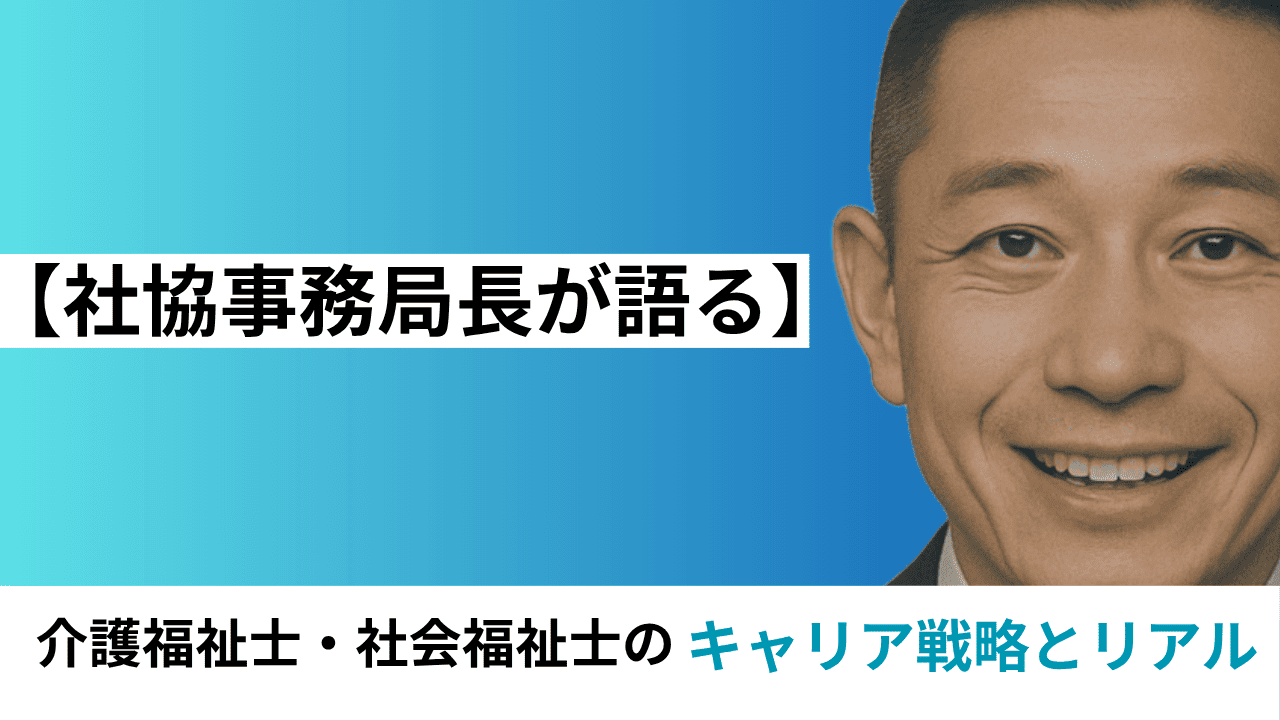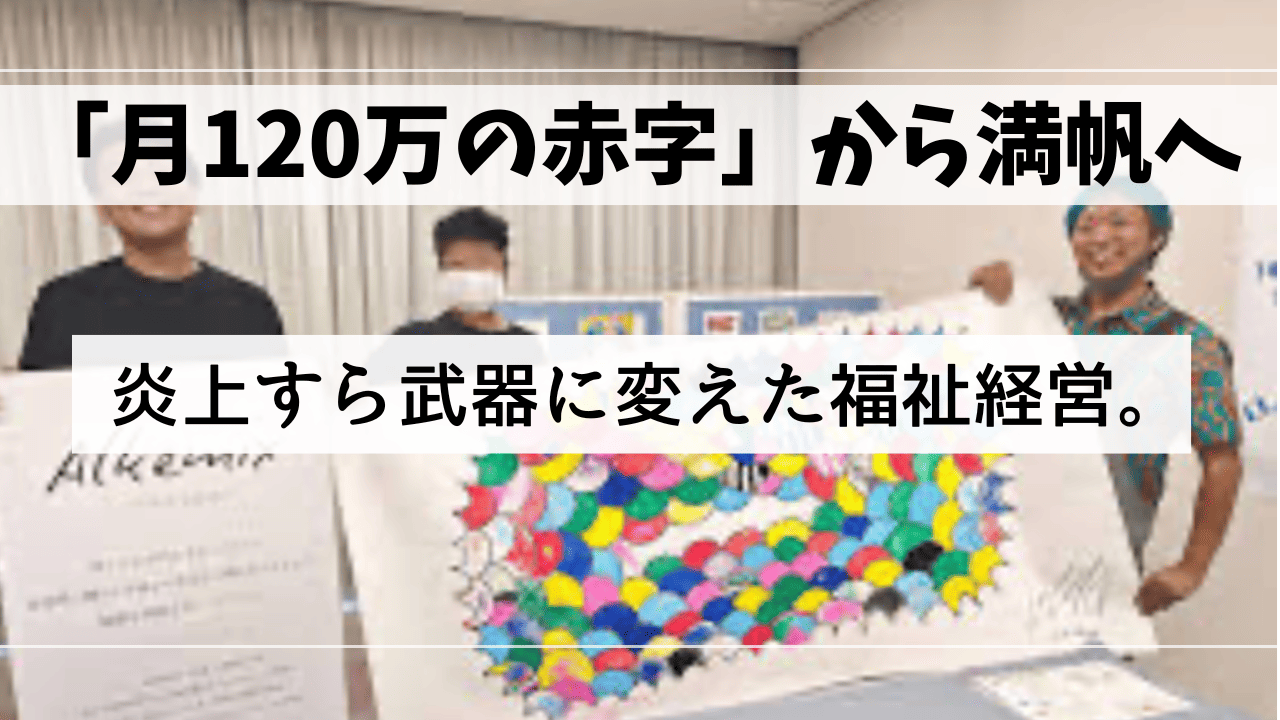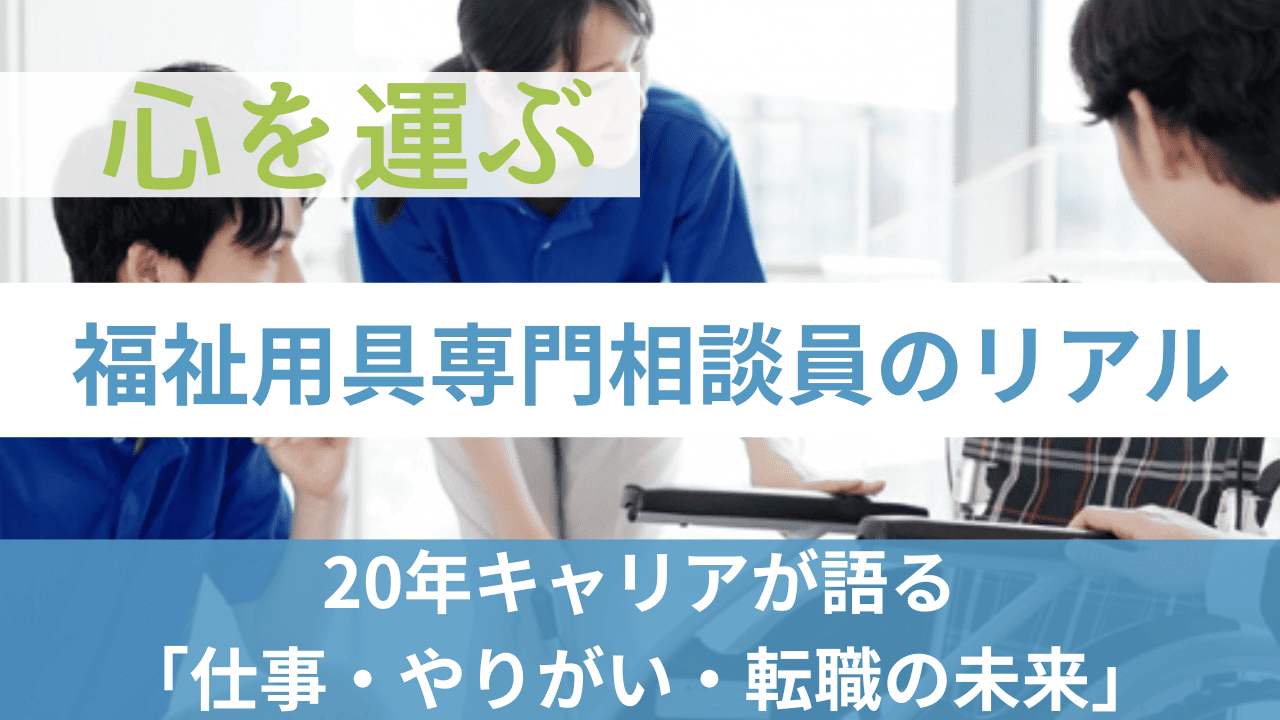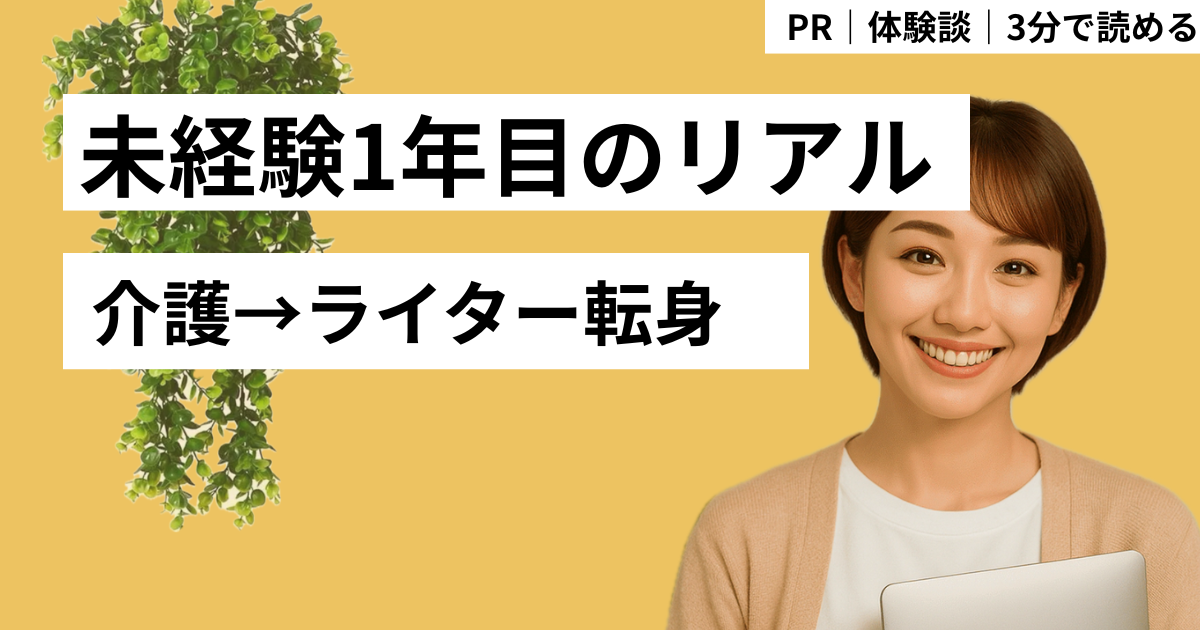※本記事にはPRを含みます
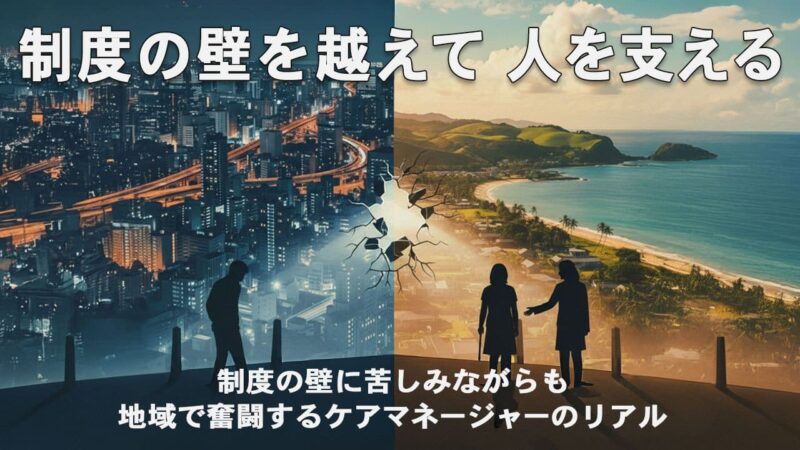
※本記事にはPRを含みます。内容はインタビューをもとに再構成したものであり、条件・制度は地域・時期によって異なります。最新情報は厚生労働省や自治体サイトをご確認ください。
制度や資格の詳細は以下の公的機関サイトをご確認ください。
▷ 厚生労働省|介護支援専門員(ケアマネジャー)制度について
▷ 全国介護支援専門員協会|ケアマネジャーの役割と倫理綱領
▷ 介護保険制度の概要(厚生労働省)
「ケアマネの仕事は、本当にありがとうで報われるのか?」
「都会のケアマネと離島のケアマネ、抱える問題はどう違うのか?」
介護業界で最も制度と現場の板挟みになるケアマネージャー。
その仕事は、担当件数の増加、介護保険への無理解、そしてゴミ屋敷や身寄りのない高齢者といった困難ケースとの戦いの連続です。
今回は、徳之島出身で福祉用具専門相談員からケアマネージャーへ転身し、現在は大阪で活躍するダイゴン氏にインタビュー。
離島と都市、それぞれの現場で直面するリアルな課題と、その中で見つけた真のやりがい、そして新しいキャリア戦略について伺いました。
この記事は、現役ケアマネはもちろん、介護職・看護職・福祉従事者、そしてこれから資格取得を目指す方にとって、未来を考えるための現場からの羅針盤となるはずです。
1. 離島と都市に見る「二重の医療格差」
ダイゴン氏は、生まれ故郷・徳之島(離島)と、現在勤務する大阪(都市)という真逆の環境でケアマネ業務を経験してきました。
その中で痛感したのは、「保険料は同じなのに、医療格差は二重に存在する」という現実でした。
離島の課題:保険料は同じでも「医療難民」
離島では、全国と同様の健康保険料を負担しているにもかかわらず、医療サービスで置いてけぼりにされています。
- 専門医の不足:脳梗塞などの急病でも、すぐに脳外科へ行けない。専門医は福岡など本土からの応援に頼る。
- 緊急時のリスク:台風で船が出ない日、蜂に刺された子どもを本土へ搬送できず、たまたま島にいた小児科医の応急処置で命が救われた事例も。
- 高額な移動費:入院・手術のために鹿児島本土や大阪へ行く必要があり、交通・宿泊費が家計を圧迫。

「健康保険料は全国とほぼ同じなのに、受けられる医療のレベルが全く違う。
これが離島の現実なんです。」
離島医療に関する課題は、厚生労働省の「へき地医療対策」でも詳しく紹介されています。
▷ 厚生労働省|へき地・離島医療対策
大阪の課題:地域格差と孤立の拡大
一方、大阪では所得格差と孤立が深刻化。地域によって利用者層が全く異なり、ケアマネ業務の難易度に直結しています。
- 北区・西区:タワマン居住の富裕層
- 港区や東淀川区など:生活保護率が高く、身寄りのない高齢者が多い
- 奄美群島では親戚が支援することが多いが、大阪では家族不在のケースが圧倒的

「入院同意書を家族が書けず、ケアマネがサインしたこともあります。
それでも誰かがやらなきゃという使命感で動いています。」
都市部の高齢者支援や独居高齢者の現状については、以下の資料も参考になります。
▷ 内閣府|高齢社会白書(孤立・地域包括支援の現状)
離島や地方での福祉経営に関心がある方はこちら👇
▶ 【炎上から満帆へ】常識を打ち破る「福祉メイキングスタジオ」の独自経営戦略とサブスク型福祉の未来
2. ケアマネージャーの課題:介護保険制度の「壁」と現場のギャップ
離島と都市に共通するのは、介護保険制度に対する誤解と無理解がトラブルを生んでいるという点です。
- 利用者の半数以上が介護保険の仕組みを理解していない
- 「認定が下りたら何でもやってもらえる」と誤解
- 「文句を言えば得をする」と考える利用者も少なくない
行政から紹介される案件は、他のケアマネが匙を投げた困難ケースであることも多く、それが若手の離職やなり手不足に拍車をかけています。

「本来の業務範囲を超えても、結局人として放っておけない。
それがこの仕事の宿命かもしれません。」
介護保険の利用範囲や自己負担についての誤解を防ぐため、
厚生労働省の「介護保険制度Q&A」も併せて確認しておくと良いでしょう。
▷ 厚生労働省|介護保険制度Q&A
3. ゴミ屋敷の現場から見えた「ケアマネの使命」
ダイゴン氏が語るのは、制度の限界を超えた人間としての支援です。
壮絶な母娘の事例
ハエとゴミだらけの家に住む母娘。娘は若年性認知症の疑い。
母親は半年間立ち入りを拒否。
母が転倒して骨折した際、「あんたが来てくれないと救急車に乗らない」と拒否。深夜に駆けつけて対応。
清掃ではダンプカー4〜5台分のゴミ、さらに娘と夫の遺骨・現金800万円を発見。
知人僧侶の協力で納骨し、最後まで看取りを支援。

「亡くなられる直前、あんたがケアマネで良かったと言ってくれた。
その瞬間、この仕事の意味をすべて理解した気がしました。」
現場で“支える人”の葛藤ややりがいについては、こちらもおすすめ👇
▶ 【福祉用具専門相談員のリアル】20年キャリアのプロが語る仕事のやりがい・給与・転職の未来
4. ケアマネージャーの課題解決とキャリア戦略
自分のキャリアを、自分で選べる時代へ。
ダイゴン氏は、制度に縛られず、

「自分の価値を自分で作る」
働き方を実践しています。
若手ケアマネに贈る4つの指針
① 専門外のスキルを身につける
介護保険の知識だけでは限界がある。
近年はChatGPTなどのAI・ITツールを活用して業務効率化を図るスキルが現場の生産性を大きく左右します。
「特許などの難しい資格よりも、日々の仕事を楽にする技術を学ぶ方が実用的です」とダイゴン氏。
② チームで“モンスター利用者・家族”に対応する
困難ケースでは、ケアマネ1人が抱え込むのではなく、多職種チームでの連携対応が不可欠。
訪問看護・地域包括支援センター・行政職員などと協働し、トラブルを未然に防ぎます。
③ 他職種の仕事を学ぶ姿勢を持つ
介護業界では低賃金・人手不足の影響から、スキルアップを避ける風潮もあります。
しかし、「他職種の仕事を理解することで、自分の視野が広がり、結果的に利用者支援の質も上がる」とダイゴン氏は語ります。
④ 組織への提言:スキル支援と“辞めない職場づくり”
「人材が育たない」のではなく、「育てる環境が整っていない」と指摘。
事業所は、ケアマネ・介護職がスキルを伸ばせる研修体制の整備と、
辞めない職場をつくる心理的安全性の確保が必要です。

「職場が“学びを支援する場所”になれば、人はもっと介護を誇れるようになる。
それが結果的に、地域や利用者の安心につながると思います。」
厚生労働省でも、介護人材の育成・定着に向けた研修や支援策がまとめられています。
▷ 厚生労働省|介護人材確保対策
地域活性化を目指す「副業」への挑戦
2025年3月より、徳之島の農産物を大阪で販売する副業を開始。
ファーマーズマーケットだけで100件以上の問い合わせ。
パッションフルーツをケーキ店と商品化し、地域還元の仕組みを構築中。

「離島の人は売るのが苦手。
私が橋渡しをして、お金が徳之島に還る流れを作りたいんです。」
介護保険外の活動を通じて、地域を救う新しいケアマネ像を模索しています。
介護職からの新しいキャリアの形を知りたい方はこちら👇
▶ 【介護の仕事は「好き」だけじゃ続かない?】元介護職の私がウェブライターに転身した理由
5. 外国人材との共生とこれからの介護現場
外国人スタッフと働く機会も多いダイゴン氏。

「彼らは日本が好きで働きに来ている。
アニメや文化への憧れもあって、前向きな人が多い。
日本はまだまだ働きたい国なんですよ。」
介護現場は多国籍化が進んでおり、外国人材との共生が未来の当たり前になる日も近いかもしれません。
外国人介護人材の受け入れに関しては、
▷ 厚生労働省|外国人介護人材の受入れ
で最新の政策や支援制度が公開されています。
多様な仲間と働ける職場で、あなたらしい介護を。
まとめ:諦めない「伴走力」こそがケアマネの未来
ケアマネージャーの仕事は、制度の壁を超えて人の人生に寄り添う仕事です。
離島では「医療格差」と闘い
都市では「孤立」と向き合い
制度では救えない人を“支える”覚悟が求められる

「結局、最後に残るのは人の笑顔なんです。
ケアマネは人生の伴走者であり続けたい。」
制度や支援の詳細は各自治体の地域包括支援センター・社会福祉協議会でも確認できます。
▷ 全国社会福祉協議会
▷ 地域包括支援センター 一覧(都道府県別)
“伴走力”を活かせる職場、見つけてみませんか?