※本記事にはPRを含みます
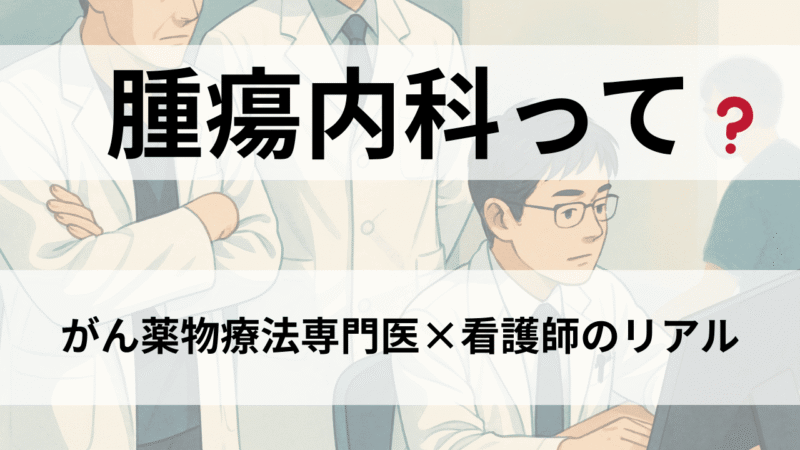
腫瘍内科ってどんな診療科?
がん薬物療法専門医は、どんな思いで患者さんと向き合っている?
医師と看護師は、チームで何を大事にしている?
今回は、腫瘍内科で働くがん薬物療法専門医の先生にインタビューし、
- 腫瘍内科医を志した理由
- がん患者さん・家族とのコミュニケーションの難しさ
- 看護師との連携で感じていること
- がん薬物療法専門医の役割と、他科との連携のリアル
をお聞きしました。
- 「腫瘍内科を知りたい医学生・若手医師」
- 「がん診療に関わる看護師」
- 「家族のがん治療を経験したご家族」
そんな方にとって、がん治療の現場の声が伝わる内容になっています。
1. 腫瘍内科医を志した理由:母の闘病から見えた地域医療の課題
母親の乳がん闘病が原点に
インタビュイーの先生が腫瘍内科を選んだ原点は、お母さまの乳がん闘病でした。
- お母さまは乳がんで亡くなられた
- 終末期に、研修先の病院と地元の医療の差にショックを受けた
- 特に「痛みのコントロール」が地元では不十分で、「ここまで違うのか」と感じた
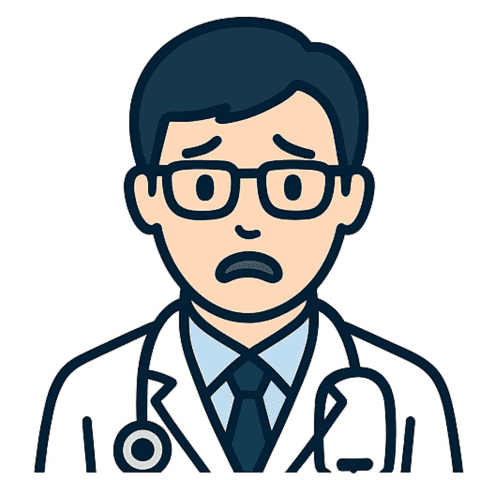
「同じ日本でも、場所によってこんなにケアが違うのか。
自分に何かできることがあるのではないかと思うようになりました」
この違和感が、先生の地域医療への問題意識につながっていきます。
内科が合っていると感じた研修時代
研修医として各科を回る中で、先生は自然と内科に惹かれていきました。
- データを見ながらじっくり考えるスタイルが好き
- 慢性疾患を含めて長く患者さんに関わることにやりがいを感じた
そこに重なったのが、ある一冊の本です。
『DIE WITH ZERO』との出会いと、母の最期の一年
先生の価値観に大きな影響を与えたのが、『DIE WITH ZERO』という書籍でした。
この本では、「お金だけを残すのではなく、人生を使い切って死のう」というメッセージが語られています。
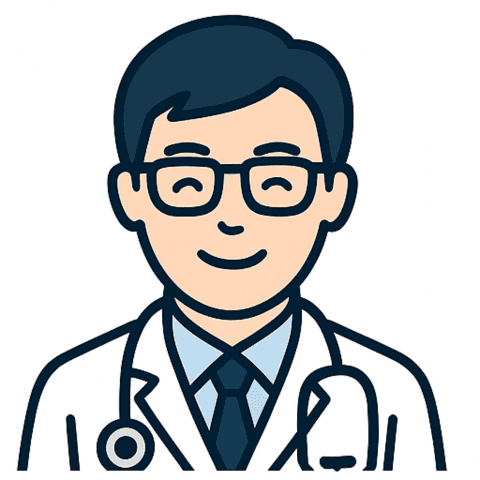
「母は最期の一年、家族旅行を何度も重ねていました。
弟は学生、自分は研修医で比較的時間の融通が利く時期で、誘われるまま一緒に旅に出ていました。
当時の自分は、ただ『子どもが社会人になって時間がなくなる前に、一緒に旅行に行きたいんだろうな』と受け止めていただけでしたが、今振り返ると『DIE WITH ZERO』のメッセージを体現していたのだと思います」
限られた時間の中で、何にお金と時間を使うのか。
その選択をそばで支える仕事として、がん診療への興味が深まっていったと言います。
※乳がん外来での告知や就労支援、検診運用の具体的な工夫については、
『乳腺外科外来の強い連携をつくる実務──告知配慮・就労支援・検診運用まで、一次情報で分かる〈詰まる所と解決策〉』
もあわせてご覧ください。
がん治療は「予後を見据えた人生設計のサポート」
先生が腫瘍内科を選んだ決め手になったのは、がん治療の特徴でした。
- がんは、ある程度「予後」を予測できる稀な疾患であること
- 予後の見通しが立つからこそ、患者さんは
- どこへ行きたいか(旅行や帰省)
- 誰に会いたいか
- どんな時間を過ごしたいか
を具体的に考えやすいこと
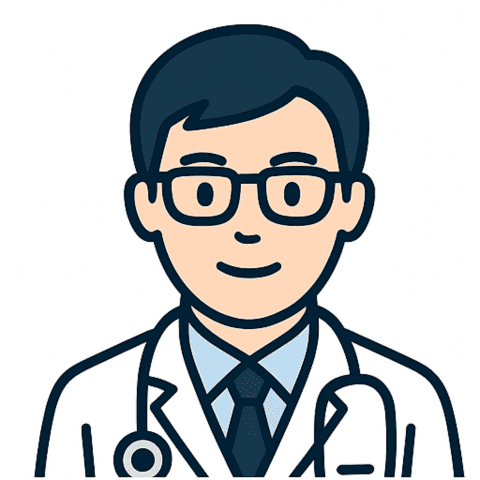
「がんの治療は、ただ寿命を延ばすだけではなく、
残された時間をどう過ごすかを一緒に考える仕事だと感じました」
「人生の最終章をどう設計するか」。
そこに伴走できることが、先生にとって腫瘍内科の大きな魅力になっています。
2. がん患者さん・家族とのコミュニケーションが難しい理由
腫瘍内科では、厳しい現実を伝える場面が少なくありません。
先生は、がん患者さん本人だけでなく、家族とのコミュニケーションの難しさも痛感していると言います。
ステージ4膵がん:「治らない病気」を受け入れられない家族
印象に残っているのは、ステージ4の膵がん患者さんのケースです。
- 診断時点で根治は難しい状況
- 先生は「治せないがんであること」「延命や症状緩和をめざす治療であること」を丁寧に説明
しかし家族はその現実を受け止められず、
- 「そんなはずはない」
- 「主治医を変えてほしい」
と強く訴えたそうです。
家族からは、こんな要望も出ました。
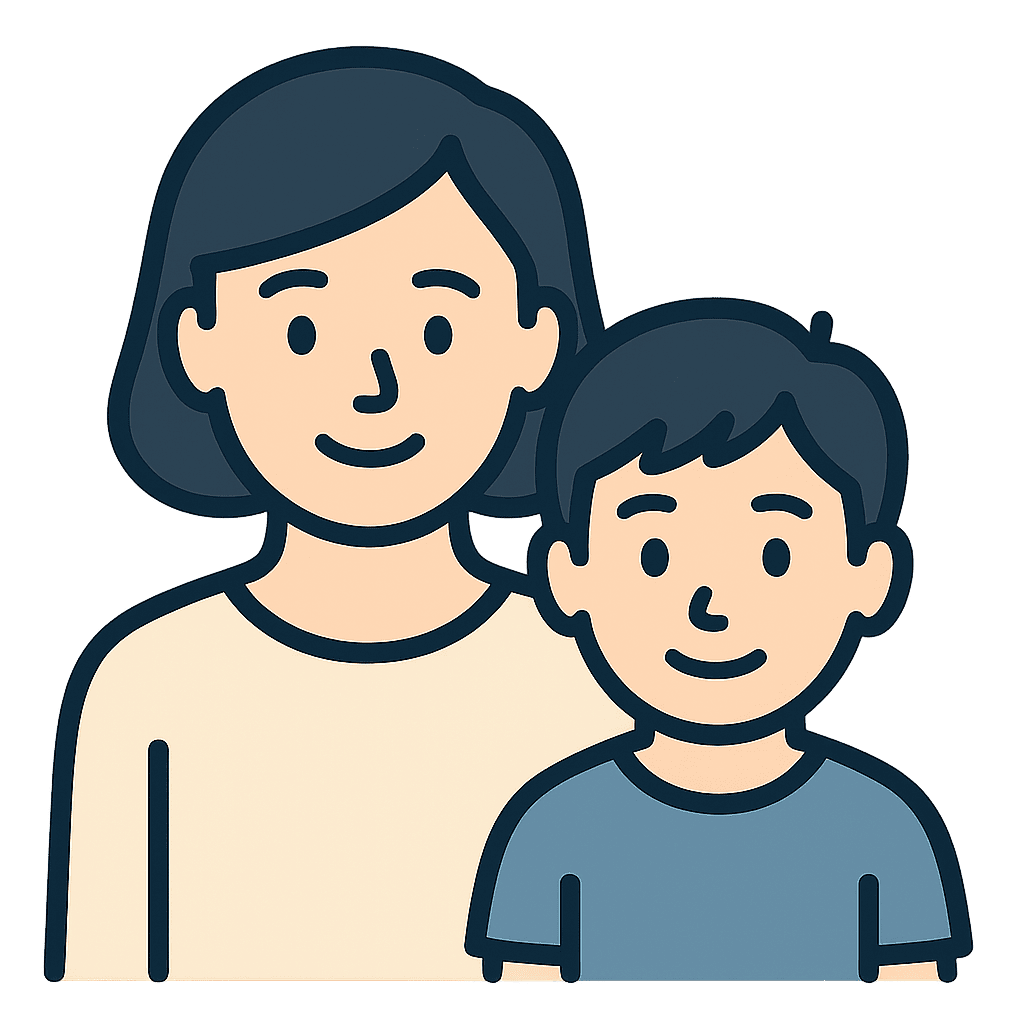
「患者本人はメンタルが弱いから、厳しい話は言わないでほしい」
しかし、治療方針を決めるためには、患者さん本人への説明と理解が欠かせません。
先生は、「本人への説明が必要であること」「ただ希望的観測だけを伝えることはできない」という点を丁寧に伝えました。
現実逃避としての「忘れてしまう」
その後も家族とのコミュニケーションは続きましたが、先生はあるねじれを感じたと言います。
- 何度も時間をかけて病状と治療方針を説明する
- それでも、家族は
- 話した内容を忘れてしまう
- 同じ質問を何度も繰り返す
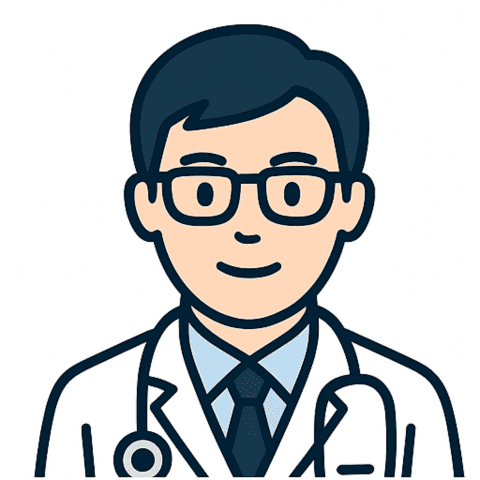
「意地悪で聞いているわけではなく、
心の防衛反応として本当に忘れてしまっているのだろうと思います」
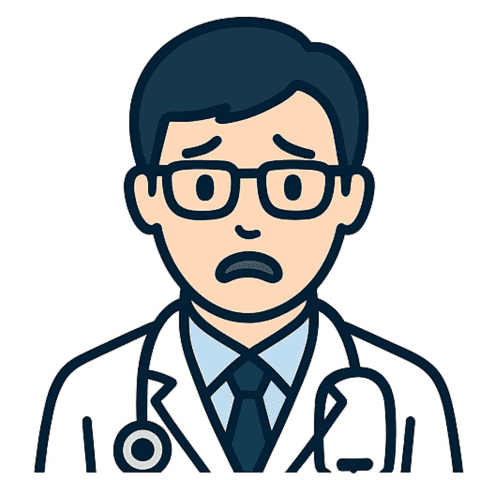
「分かりたくない現実は、頭からこぼれ落ちてしまう」
がんという病気の重さゆえに生じる、家族の心理的防衛。
先生は、「もっと初期の伝え方や支え方を工夫できたのでは」と自問することもあると話します。
3. 多職種連携での医師と看護師の役割:記録と「本音」の橋渡し
がん診療は、医師だけで完結するものではありません。
先生はインタビューの中で、看護師の存在と役割について何度も触れていました。
「看護師記録」は、医師にとっての『患者さんの声』
先生が特に重視しているのが、看護師の記録です。
- 診察室では、患者さんは医師を前に気を遣ってしまうことがある
- 医師の前では「大丈夫です」と言っていても、病室では不安や本音を漏らしているケースは少なくない
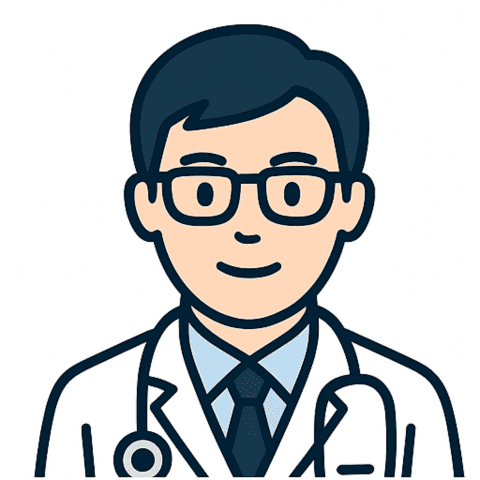
「IC(説明と同意)のあと、病室で
『本当は怖い』『家族に迷惑をかけたくない』
と話していることを、看護師さんが記録や口頭で教えてくれます。
それが、患者さんの感情を理解する上で本当に大きいんです」
ここで先生が「ありがたい」と感じているのは、
医師の説明を翻訳してくれることそのものというよりも、
- ICの内容を患者さん・家族がどう受け取ったのか
- どこまで理解できているのか
- その内容を聞いて、どんな感情の反応が出ているのか
を、観察と記録を通して多職種チームに共有してくれる点です。
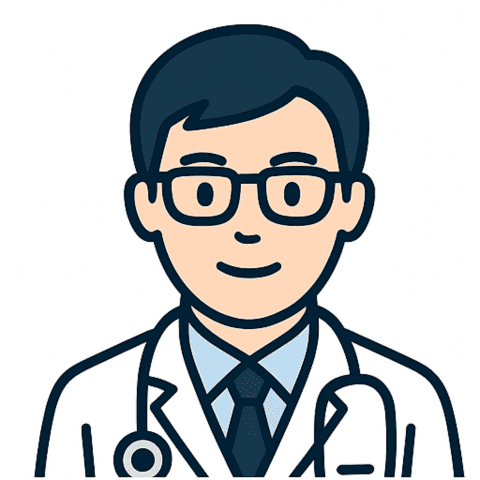
「反応は、言葉だけではなく、
帰室後のふるまいや表情、ご家族との接し方にも表れます。
そうした様子を看護師さんが教えてくださることで、
今後どのように話していくか・接していくか、
社会的サポートをどの程度用意すべきか、チームで相談できるようになります」
インフォームド・コンセントの実際の進め方や「言いづらいこと」をどう伝えるかについては、
『産婦人科医35年が語る──インフォームド・コンセントと“命の現場”のリアル』
でも詳しくお聞きしています。
カンファレンスでの看護師の役割
先生は、カンファレンスの場での看護師の役割についてもこう語ります。
- 患者さん本人の不安
- 家族の最大の困りごと
- 生活面・心理面での課題
これらを一番よく把握しているのが、日常的にそばにいる看護師です。
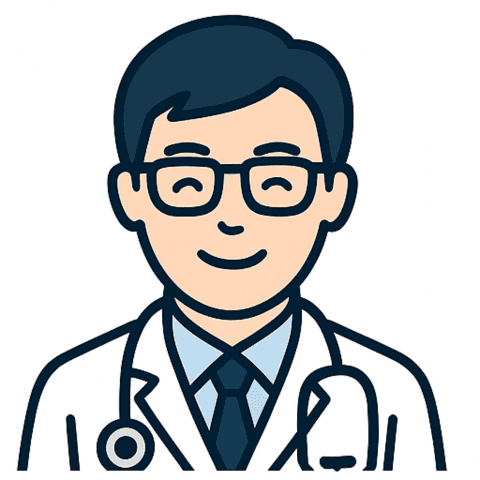
「患者さんの全体像をチームに伝えてくれるのが看護師さん。
その情報があるからこそ、
治療だけでなく生活も含めたケアの方針を決めることができます」
カンファレンスでは、
- 「今いちばん困っているのは、痛みか?不安か?家族のケアか?」
- 「退院後の生活で、どこにリスクがありそうか?」
といった視点を、看護師が現場の情報と結びつけて共有してくれることが重要だと感じているそうです。
さらに先生は、看護師による感情面のサポートの意義も強調します。
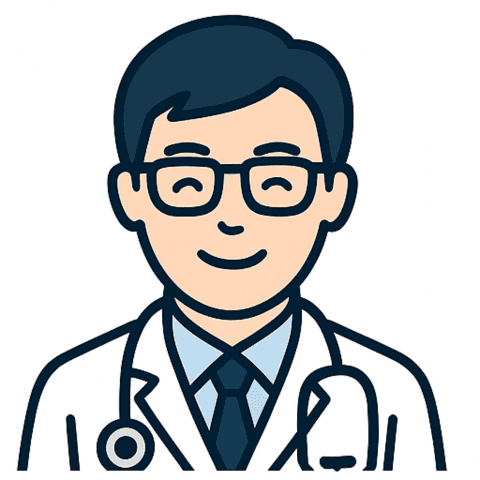
「いずれ来る終末期を思って不安になる患者さんの気持ちに寄り添っていただけることは、
治療に前向きに取り組むきっかけにもなります。
とてもありがたく考えています」
看護師は、
- 患者さん・家族がICを「どう理解し、どう感じたか」をチームに伝える存在であり、
- 不安に寄り添い、治療へ向かう気持ちを支えてくれる存在
として、がん診療に欠かせないパートナーになっています。
4. がん薬物療法専門医とは?役割と他科との連携のリアル
ここからは、インタビュアーである先生が専門とする「がん薬物療法専門医」について、少し掘り下げていきます。
がん薬物療法専門医=臓器横断の「横割り」内科医
先生は、自身の役割をこう表現します。
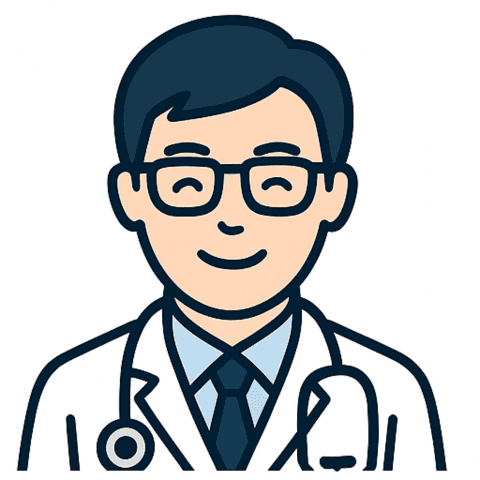
「がん薬物療法専門医は、臓器横断的にがん全般を診る横割りの診療科です」
乳がん・肺がん・消化器がん…と、臓器ごとに縦割りの診療科がある一方で、
がん薬物療法専門医は、抗がん剤・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬などの薬物療法を横断的に扱う内科医です。
特徴としては、
- 幅広い治療レジメンの知識
- 副作用マネジメントや支持療法のノウハウ
- 「看取り」までを視野に入れた治療計画
を専門にしている点があります。
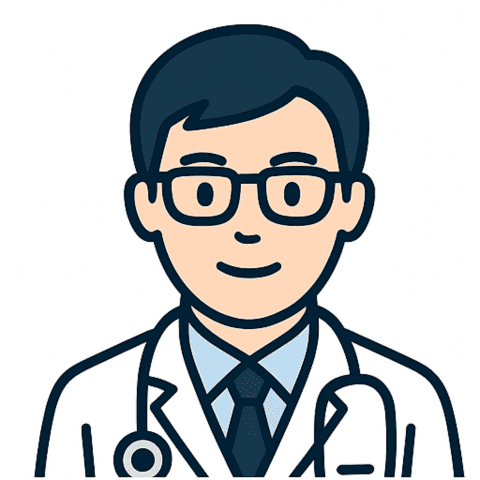
「単にガイドライン通りに、杓子定規に延命目的の化学療法を導入するだけではありません。
患者さんの状態や、大事にしている生活・仕事、避けたい副作用のプロファイルを踏まえて、
有効と言われている治療選択肢をどの順番で選ぶかを組み立てていきます」
先生は、印象に残っている症例として、こんなエピソードを話してくれました。
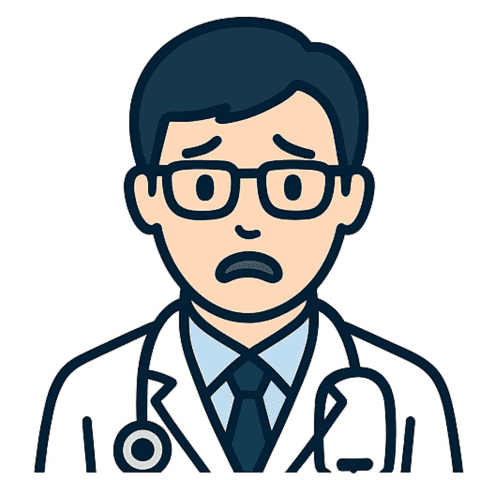
「例えば、大腸がんの方がいました。
その方にとっては指先の感覚が何より大事なので、
末梢神経障害をきたしやすいオキサリプラチンは前半のラインでは使わず、
より後方ラインでの投与を検討するといった判断をしました」
どの薬をどのタイミングで使うのかだけではなく、
- 治療をどのタイミングでやめるのか
- どこで最期を迎えたいのか
といった「人生の設計」も含めてトータルに考える。
それが、先生の考える腫瘍内科・がん薬物療法専門医の役割です。
連携が難しいと感じる他科のパターン
一方で、他科との連携で課題を感じる場面もあります。
先生が「連携しづらい」と感じるのは、次のようなパターンです。
- 患者さんを丸投げしてしまうケース
- 「もう治療はできないから、あとは腫瘍内科で」と、説明や関係性の引き継ぎが不十分なまま転科になる場合
- 治らないと分かっているのに、安易な希望を与えてしまうケース
- 「新しい薬があるらしいから、まだ大丈夫」といった希望的観測だけを伝えてしまう
その結果、腫瘍内科で正確な説明をした際に、患者さん・家族が大きなショックを受けることがあります。
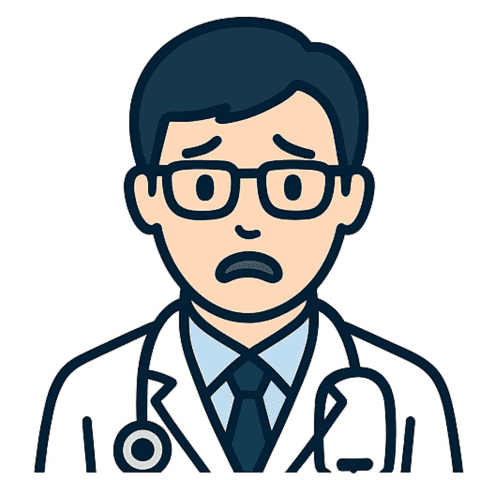
「重い話をするのは、どの医師にとっても負担です。
でも、事実と違う希望を伝えてしまうと、患者さんや家族が後で余計につらくなってしまいます」
「前の先生から、何と聞いていますか?」から始める
他科から紹介された患者さんを診るとき、先生が最初に必ず確認するのがこの一言です。
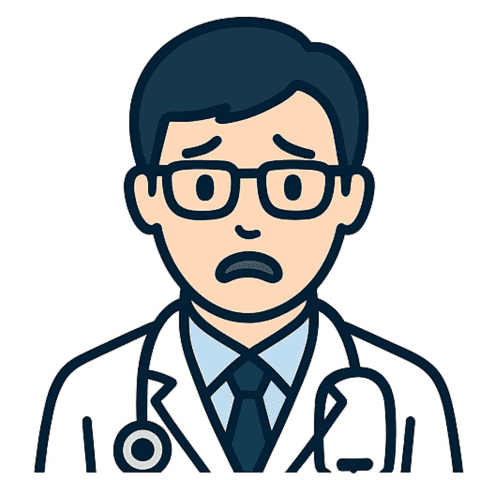
「前の先生から、どのように説明を受けていますか?」
- まずは患者さんが今持っている認識を確認する
- そのうえで、足りていない情報を補う
- 誤解があれば丁寧に訂正する
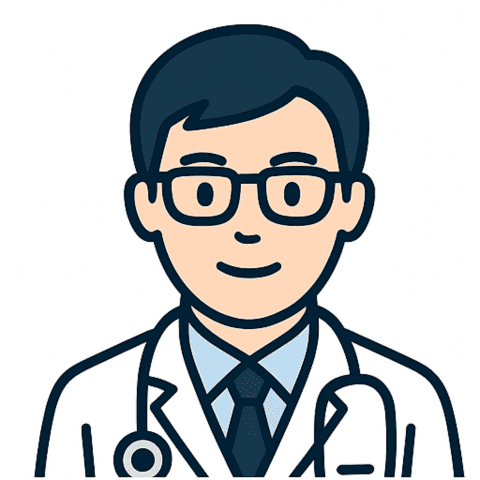
「前医を批判するのではなく、
患者さんの頭の中の地図を正しく書き換えていくイメージです」
腫瘍内科の役割は、最後に真実を告げる係ではありません。
「今の病状」と「これからできること」を、
患者さんの人生の文脈の中で一緒に考えるパートナーだと、先生は考えています。
5. これから腫瘍内科・がん診療を目指す人へのメッセージ
腫瘍内科は「医学」と「人生」が交差する場所
予後予測や治療選択など、医学的な判断が求められる一方で、
患者さんの価値観・家族の背景・地域の医療資源など、人生そのものに踏み込む対話が必要になる診療科です。
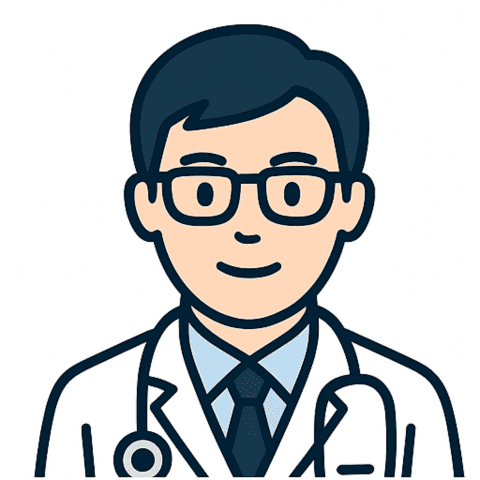
「つらい場面も多いですが、
『あのとき一緒に考えてくれてありがとう』と言ってもらえる時、
腫瘍内科を選んで良かったと心から思います」
看護師・コメディカルとの連携が『良い医療』を作る
先生はインタビューの中で何度も、看護師の存在の大きさを語っていました。
- 患者さん・家族がICをどう理解し、どう感じたかを教えてくれる
- 病棟での様子や生活の困りごとを伝えてくれる
- 不安に寄り添い、治療に向き合う力を引き出してくれる
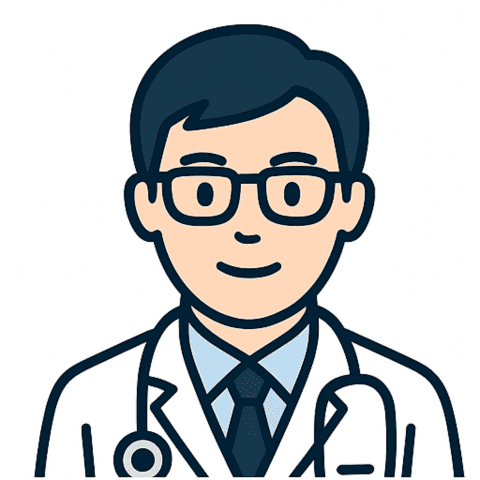
「一人の医師でできることには限界があります。
看護師さんや多職種の力を借りることで、やっとチームとしてのがん医療になると感じています」
まとめ
このインタビューを通して見えてきた、腫瘍内科・がん薬物療法専門医の姿を改めて整理すると――
- 原点には、身近な人のがん闘病と地域医療の格差への問題意識があった
- がん治療は、「寿命を延ばす」だけでなく、「残された時間をどう生きるか」を一緒に考える仕事
- 家族が現実を受け止められず、何度も同じ質問を繰り返すこともある。それは意地悪ではなく、心の防衛反応でもある
- 看護師は、ICをどう理解しどう感じたか、帰室後のふるまいや家族との関わりも含めて共有してくれる存在
- その情報をもとに、多職種チームが「今後どう話し、どう支えるか」を相談できる
- がん薬物療法専門医は、臓器横断的にがん全般を診る「横割り」の内科医であり、
- 副作用や生活背景を踏まえた治療の順番を考える
- どこまで治療を続けるか、どこで最期を迎えるかまで含めてトータルに設計する役割を担っている
腫瘍内科は、医学的な「正しさ」と、患者さんの「生き方」が、毎日のようにぶつかり合う現場です。
だからこそ、
- 患者さん・家族の声に耳を傾ける看護師
- 現場の負担を分かち合う多職種チーム
- 誠実に「今できること・できないこと」を伝える医師
その全員がそろって初めて、その人らしい最期までを支えるがん診療が成り立つのだと感じさせられるインタビューでした。
もしこの記事を読んで、
- 腫瘍内科やがん薬物療法専門医の仕事に興味がわいた
- がん診療に関わる看護師として、もっと連携の質を高めたいと感じた
という方は、ぜひ自分の職場でのカンファレンスや記録のあり方を、今日から少しだけ見直してみてください。
それが、目の前の患者さんと家族の「人生の最終章」を支える一歩になるはずです。
▶︎ がんと診断された方・ご家族の相談窓口を探す(がん相談ホットライン)