※本記事にはPRを含みます
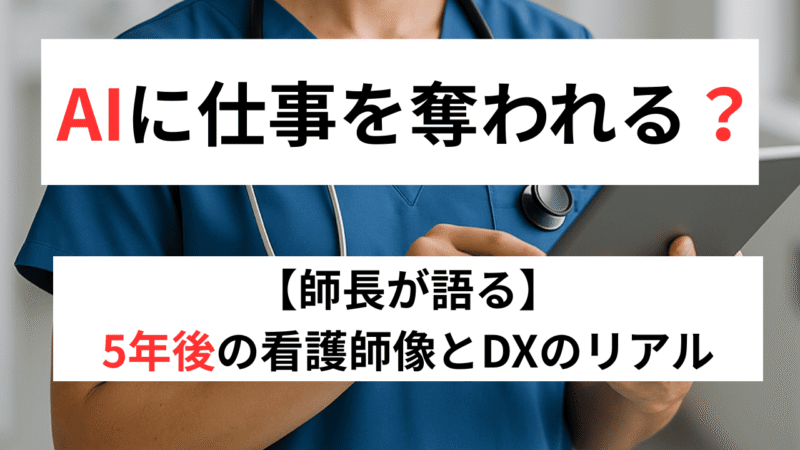
💬「看護師ってキャリアの選択肢が少ない?」
💬「AIに仕事を奪われる未来が来る?」
こうした不安や疑問に答えるため、小児科一般病棟→ICU→成人ICU→一般病棟の師長と多彩なキャリアを歩み、現在は医療DX推進やAI活用にも携わるベテラン看護師にインタビューしました。
医療業界のIT化の現状、地方と都市の看護師格差、離職を防ぐ採用戦略、そして5年後の看護師像まで――リアルな声をまとめます。
1. 医療業界のDXはなぜ遅れているのか
結論:医療現場はIT化が非常に遅れている。
「医療=最先端」というイメージがありますが、実際には電子カルテ以外のIT導入は進んでいません。
- データ連携が不十分
- 紙文化が根強い
- 管理は「経験と度胸」頼み
👉 この遅れを解消するため、ポータルサイト導入やデータ基盤整備が始まりつつあります。
2. 小児科を選んだ理由
結論:看護師への不安を和らげる“癒し”を求めて小児科を選択。
- マルチタスクに対する不安から、小児を対象とした診療科を志望。
- 実習では小児科が苦手だったが、父親の「自分にとってメリットがある場所を選べ」という助言で考えが変わった。
3. 小児ICUへの挑戦
結論:一般病棟でのスキル限界を感じ、スキルアップのため小児ICUへ。
- 出血を見抜けなかった経験から、「もっと学ばねば」という危機感が芽生えた。
- ICU異動後は血圧の基礎から徹底的に勉強し直し、学習量が飛躍的に増えた。
4. 成人ICUでのスキル習得
結論:小児科では経験できない基本技術を学ぶため、成人ICUへ。
- 小児科では医師が実施するため、看護師は抹消ライン確保を経験できない。
- 同級生ができる技術を自分ができないことに劣等感を抱き、成人ICUで基礎スキルを磨く決意をした。
5. 一般病棟の師長へ──キャリア再出発
結論:ICUでの管理職経験後、部長の配慮で成人一般病棟の師長に。
- ICU師長代行時代は、若手休職が相次ぎ、自身も精神的に追い詰められた。
- そこで部長が「環境を変えた方がいい」と判断し、成人一般病棟の師長に。
- 未経験の領域でも、副師長の支えを得て再スタートできた。
6. 離職問題の本質と採用ミスマッチ
結論:離職の原因は人間関係より“職場環境と適性のミスマッチ”。
- 急性期病院(稼働率95%)に、療養型出身の看護師が適応できず連続退職。
- 結果、日勤を8人→6人で回さざるを得なくなり、精神的に落ち込んだ。
- 対策は「採用段階でのミスマッチ回避」が不可欠。
7. 看護師確保と地域格差
結論:地方は“育成環境不足”、都市部は“競争激化”。
- 種子島など離島には看護学校がなく、若手が育たない。
- 関東でも少子高齢化により労働力が不足。
- どちらも看護師確保に苦労しており、データに基づいたマネジメントが重要と指摘。
8. データ活用の工夫
結論:看護師の目標と数値を連動させることで改善が進んだ。
- 単に「稼働率」「褥瘡率」を提示しても、現場には響かなかった。
- 個々の目標と紐づける形にすると、自分ごととして改善意識が芽生えた。
- 紙集計からデジタル移行したことで効率化も実現。
9. DX導入の現場の反応
結論:ポータルサイト導入は利便性が勝り、大きな抵抗はなかった。
- 「どこにあるか分かりにくい」という声もあったが、情報が一元化され便利に。
- 管理職層が前向きだったため、導入はスムーズに進んだ。
10. 5年後の看護師像とAIの役割
結論:AIが定型業務を担い、人間性こそが評価される時代へ。
- AIが記録作成や体調確認を担う未来はすでに始まっている。
- 実際に患者との会話をAIがSOAP形式に要約する取り組みを試行中。
- 「不機嫌な看護師は淘汰される」――AI時代はヒューマンスキルが価値になる。
11. 認知症患者とAIの可能性
結論:発話困難でも、看護師が仲介役となればAI活用は可能。
- 看護師が観察し、状況を言語化してAIに入力することで対応可能。
- 観察力・解釈力そのものがAIに組み込まれる未来も期待される。
まとめ
※本記事内には、相互リンクのための紹介リンクを含みます。
このインタビューから見えてきたのは、
- 看護師のキャリアは一つではない
- DXやAIは仕事を奪うのではなく、人間らしさを際立たせるチャンス
ということでした。
👉 医療のDXが進むこれからの時代、看護師に求められるのは「技術」だけでなく、患者を理解し寄り添う力。
挑戦と学びを続けることが、キャリアを切り開く最大の武器になるでしょう。
DXやAIは仕事を奪うものではなく、人間らしさをより際立たせるためのチャンスです。
患者と向き合う時間を確保するためには、DXやAIを活用し、パソコン作業に追われる時間を減らしていくことが欠かせません。
介護・看護ソフトの「トリケアトプス」は、こうした新しい働き方や価値観を後押しするツールです。
日々の記録業務や煩雑な書類作成、レセプト業務を効率化することで、ケアに充てる時間を生み出し、患者の心に寄り添うための時間を確保できます。