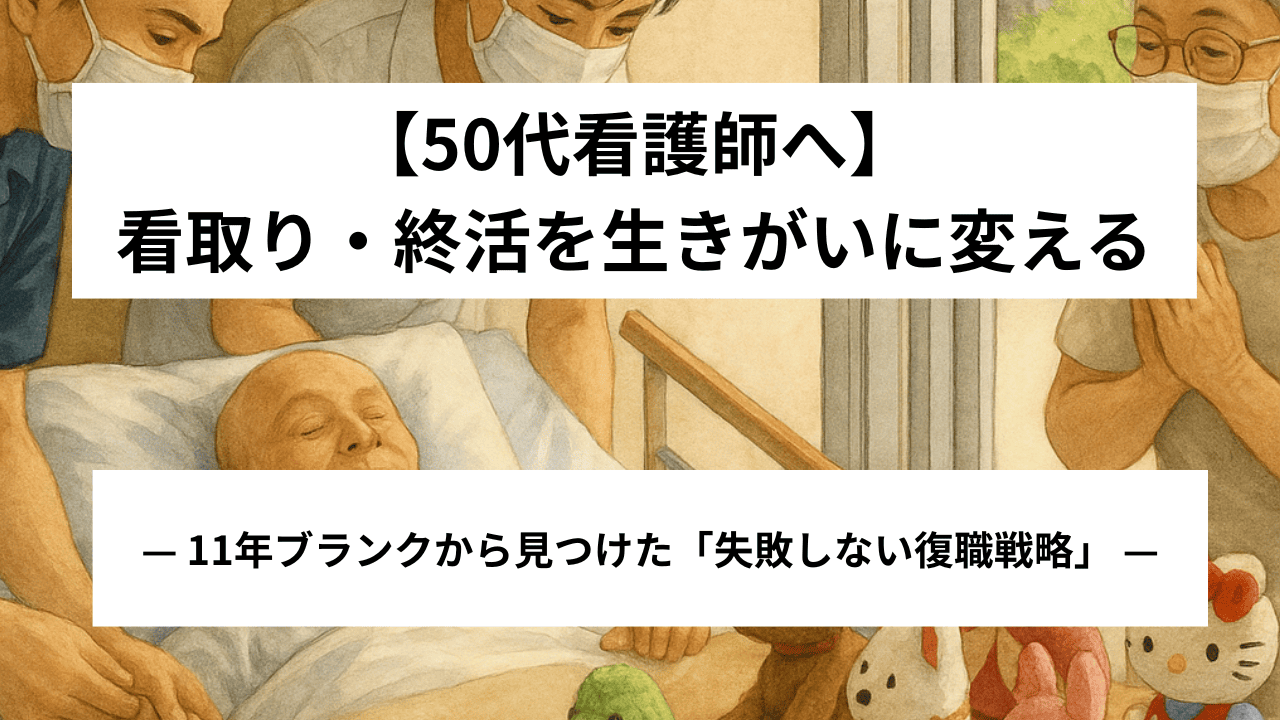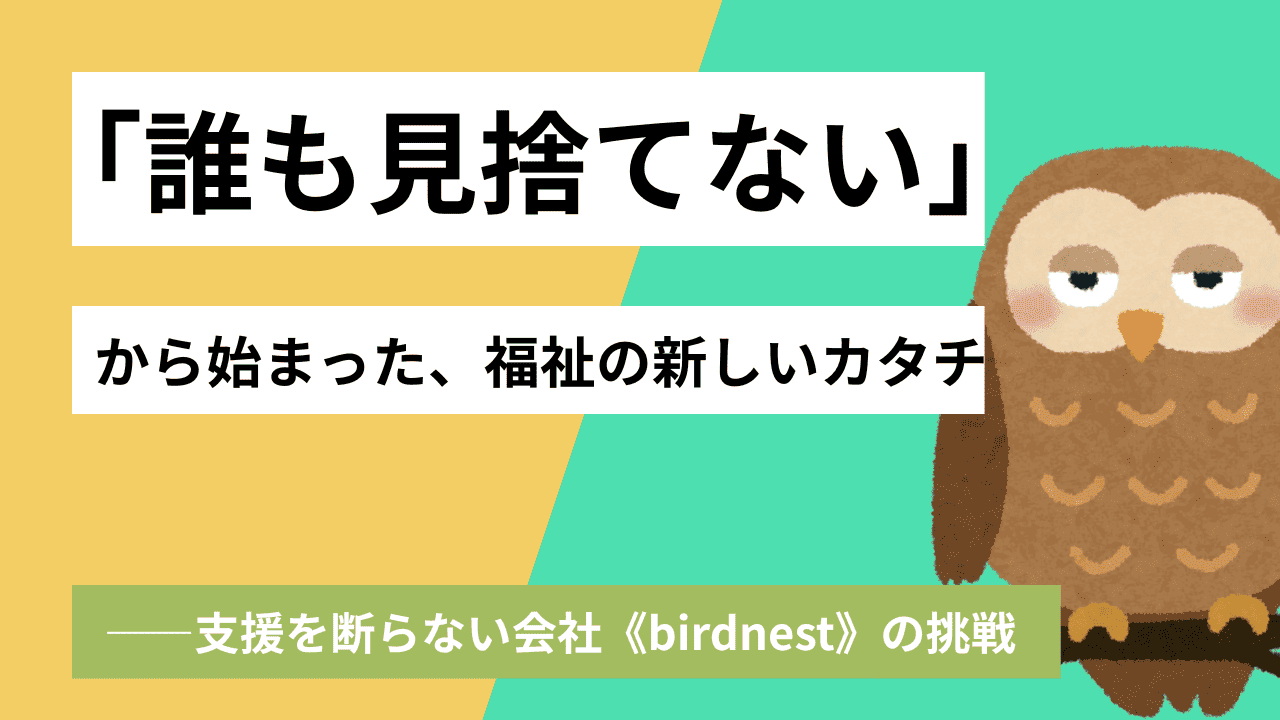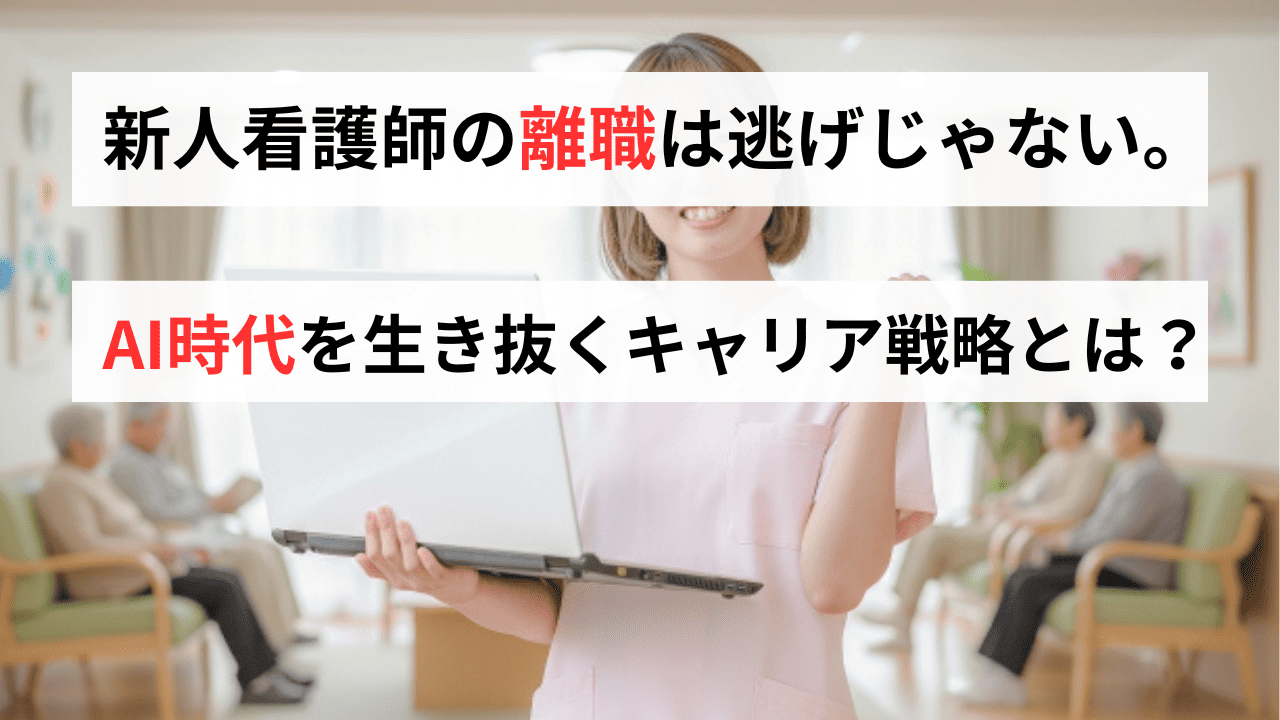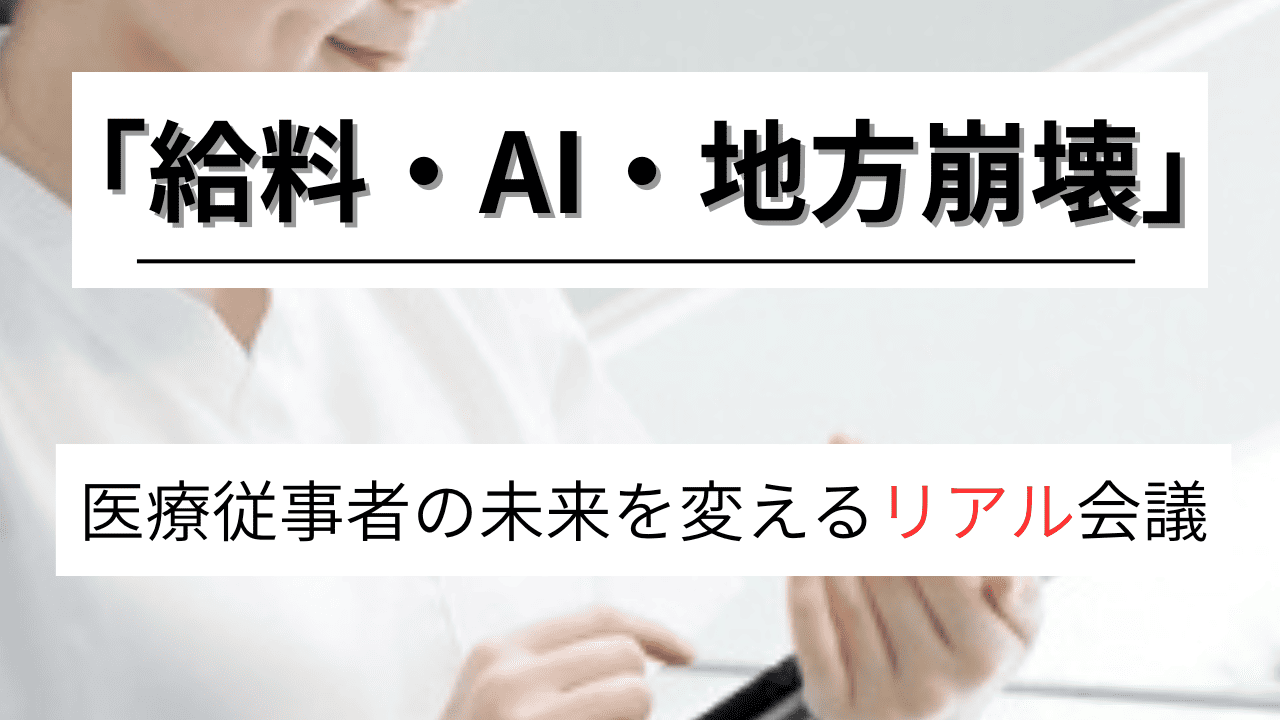※本記事にはPRを含みます
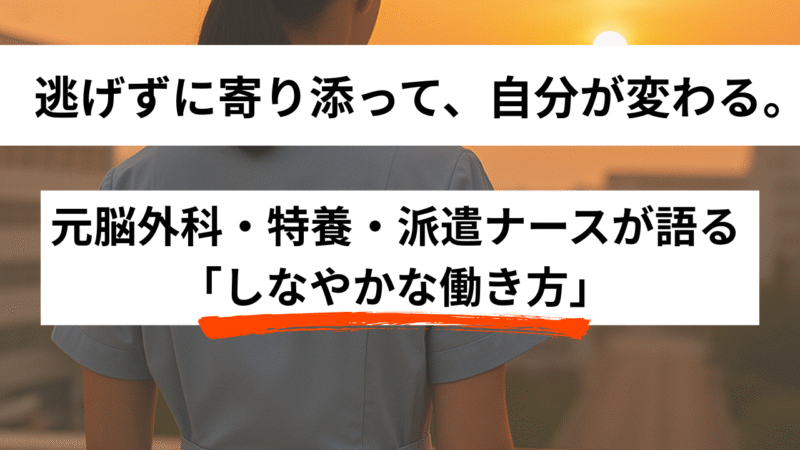
最終更新日:2025年10月19日
※内容は実際のセミナー会議での発言をもとに再構成しています。個人の見解を含み、所属組織や医療方針を代表するものではありません。
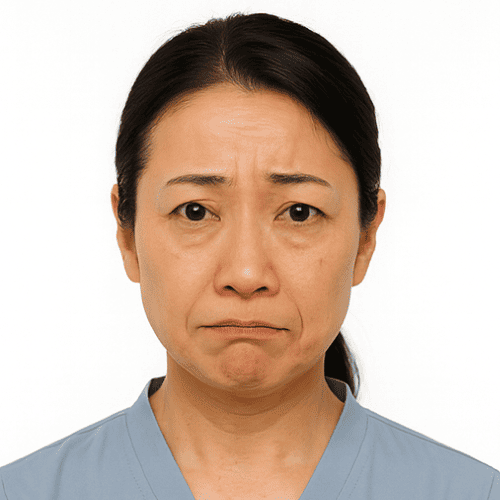
「逃げたい」と思うあなたへ
あなたは今、看護師としてのキャリアに悩んでいませんか?
「職場の人間関係が辛い」
「ブランクがあるから復職が怖い」
「このまま今の職場でいいのか分からない」
——そう感じているのは、あなただけではありません。
本記事では、産婦人科・脳神経外科・特別養護老人ホーム(特養)・デイサービス・派遣・ツアーナースと、さまざまな現場を経験してきたベテラン看護師の実体験を紹介します。
壮絶ないじめ、10年のブランク、職場で身内を介護するという現実——。
それでも彼女が「逃げずに現状に寄り添い、自己変革を続けられた理由」を、リアルに掘り下げていきます。
1. キャリアの原点 実務重視の教育と最初の「電撃退職」
1-1. 全日制を選ばなかった理由:「現場で通用する力をつけたかった」
高校卒業後、彼女は全日制の看護学校ではなく、働きながら学べる産婦人科病院併設コースを選びました。
きっかけは、高校の同級生のひと言でした。

「全日制の子は知識はあるけど、現場では役に立たないんだよ」
この言葉が胸に残り、「実践力こそが本物の看護」と考えたのです。
現場で患者さんと接しながら学ぶ日々は、厳しくも大きな成長につながりました。
1-2. 危険な医療行為と、学費返金を伴う退職
しかし、卒業後に就職した産婦人科クリニックでは、驚くべき現実が待っていました。
院長医師の医療行為が、学校で学んだ内容と真逆。安全管理も倫理も欠如していたのです。
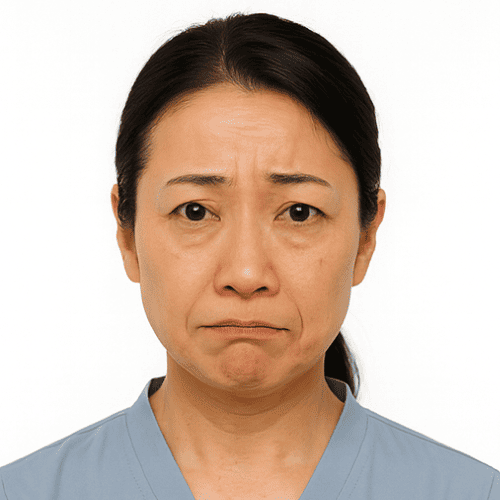
「このままでは命が危ないと思った。怖かった。」
お礼奉公の代わりに、支援を受けた学費を全額返金して退職。
信念と倫理観を守るための、若き日の決断でした。
2. 脳神経外科で直面した「いじめ」と、その乗り越え方
👉 「職場の人間関係がつらいと感じたら、こちらの記事も参考になります。」
【看護師1年目あるある】辞めたい・つらい・毎日泣く…そんな日々の乗り越え方
2-1. キャリアアップのための挑戦と試練
次に選んだのは、外科・脳神経外科。
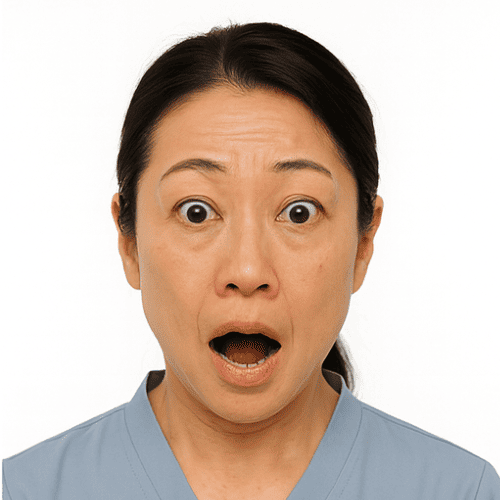
「外科で3年やればどこでも通用する」
そう信じて転職しましたが、現実は過酷でした。
多忙な職場で、先輩看護師から1年間にわたるいじめを受けたのです。
当時21歳。相手は子育て中のベテラン看護師でした。
2-2. いじめを乗り越えた 2つの思考法
1️⃣ 患者に集中する

「自分を必要としてくれる患者に意識を向けた。」
周囲の言動ではなく、目の前のケアに全力を注ぐことで、心を守りました。
2️⃣ 「いつまで働くか」のゴールを設定する

「何月何日までと期限を決めたら、少し楽になった。」
逃げるのではなく、自分で出口をコントロールする感覚が、心を支えました。
3. 特養への転職と、身内を介護するという現実
3-1. 祖母が入居する施設での勤務
いじめを乗り越えた彼女の次の転機は、祖母の介護でした。
祖母が認知症を発症し、神奈川県の特別養護老人ホームに入居。
彼女はその施設に転職し、看護師として祖母の面倒を見ることに。
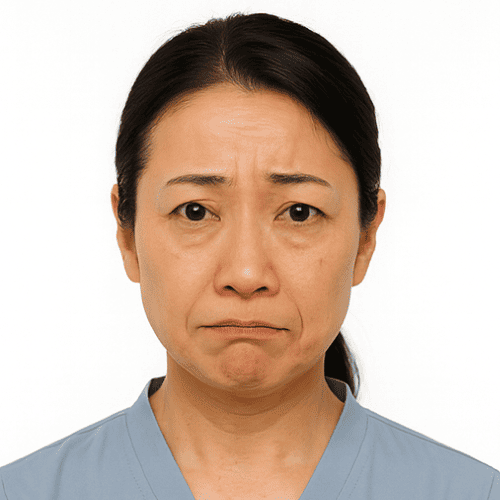
「祖母も、他の入居者も患者じゃなくて生活者。
だからこそ、特別扱いしないと決めていた。」
3-2. 骨折をきっかけに感じた「介護の現実」
祖母が骨折をしたことで寝たきりになり、認知症が一気に進行。
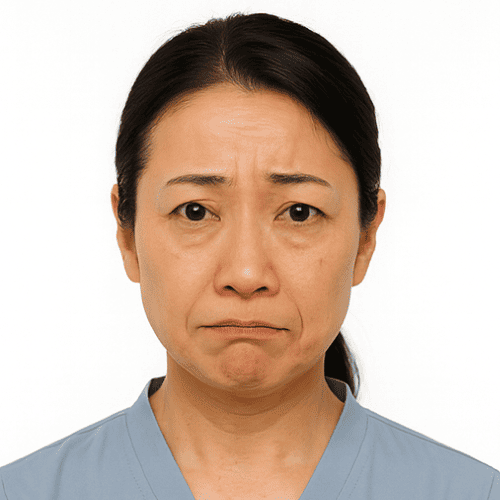
「もうだめだなって思った。あの瞬間が一番辛かった。」
この経験が、彼女の看護観をさらに深めました。
——人を看るとは、治すことだけではない。寄り添うことだ。
4. 10年のブランクと「再出発」への挑戦
👉 「ブランクを経て現場復帰した看護師の体験談はこちらでも詳しく紹介しています。」
4-1. 復帰のきっかけは「介護保険制度」
2000年の介護保険導入により、夫の収入が減少。
生活のために、10年のブランクを経て再び看護師の道へ戻る決意をしました。
4-2. 医療器具が進化した 転換期 に救われた
復帰した2002年当時は、ちょうど医療現場が大きく変わる時期。
点滴の針が金属からプラスチック製に変わり、現場の誰もが手探り状態でした。

「みんな初心者だった。だから一緒に学べた。」
その偶然の追い風が、ブランクを乗り越えるきっかけになりました。
4-3. 現在は「看護師が選ぶ側」の時代へ
昔は雇ってもらえるだけでありがたい時代。
しかし今は人手不足で、看護師は完全に「選ぶ立場」です。

「ただ、求人票だけでは分からない。
本当の現場を見極める力が大切。」
彼女は現在、ブランク看護師向けに「病院選びのアドバイス」を発信しています。
5. 介護施設と病院の決定的な違い
👉 「介護と医療の現場でやりがいをどう見つけるか、こちらの記事でも紹介しています。」
5-1. 介護施設は「治す場所」ではなく「暮らす場所」
病院が治療の場であるのに対し、
介護施設は「生活の場」です。
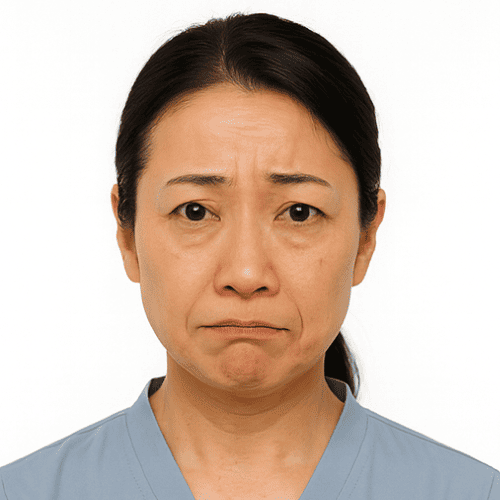
「病院のような完璧な衛生観念を求めすぎると、続かない。
自分がどこまで対応できるかを決めることが大事。」
5-2. デイサービスは 楽しみ と 危険 が共存
デイサービス勤務歴6年の彼女。
窒息・意識低下などの対応が求められる一方で、利用者と笑顔を共有する瞬間も多いと言います。
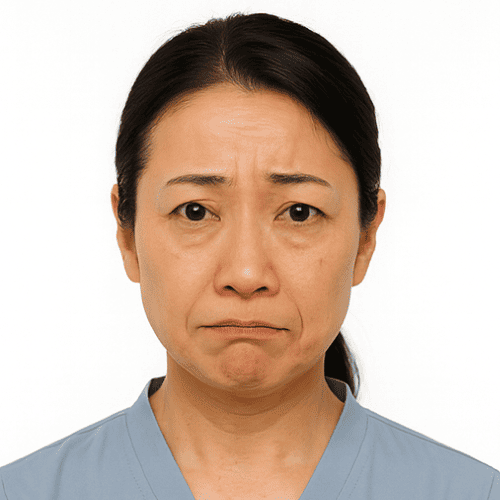
「緊急対応のリスクが高いから、新人がいきなり入るのは危険。」
経験を積んだ看護師にとっては、看護観を広げる最高の現場です。
👉 介護保険制度の概要は
厚生労働省|介護保険制度について が詳しいです。
6. 新人看護師への3つのアドバイス
👉 「新人看護師の離職やキャリアに悩んでいる方はこちらの記事も参考になります。」
6-1. 辛い現実に「逃げないで寄り添う」

「どこまでも逃げないで、今ある現状に寄り添ってほしい。」
患者の状態悪化や死を前にしても、逃げない姿勢が看護の本質です。
6-2. 認知症ケアは「イライラしない工夫」から
認知症看護で最も重要なのは「イライラしないこと」。
気持ちを紛らわせる工夫をしながら、自分を守ることも看護の一部です。

「まずは上手な先輩の真似から始めて。」
6-3. 「鬼滅の刃」が教えてくれた自己変革
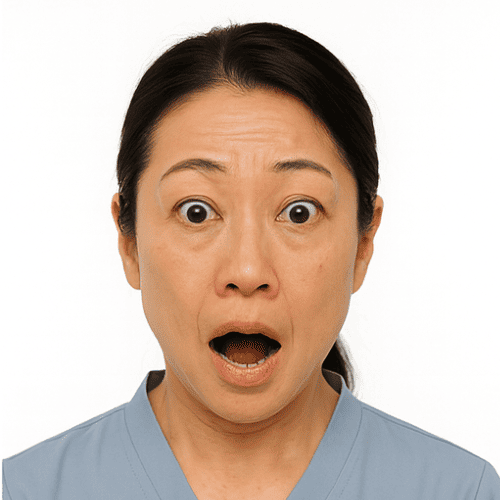
「他人を変えようとするより、自分が変わる。」
ゼロか100かの完璧主義をやめ、中間の「50」の思考を持つこと。
それが、長く働き続けるための秘訣だと語ります。
7. 看護師教育の「仕組み」への疑問
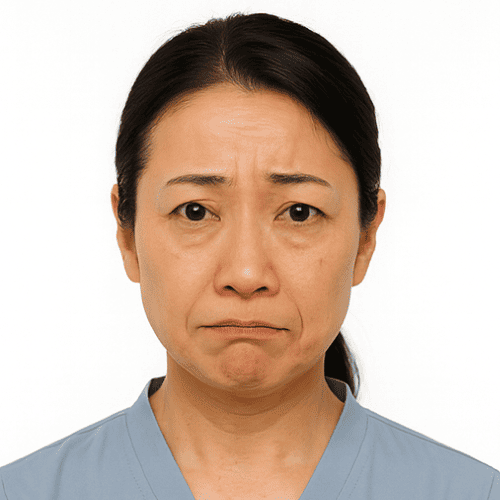
「今の仕組みのままでは、子どもに看護師を勧められない。」
教育課程や実習制度など、看護師になるまでの過程に無理が多い。
これが離職率や志願者減少の一因になっていると指摘します。
8. AI分析で見えた3つの課題
1️⃣ 新人看護師のリスク管理体制
デイサービスなど高リスク環境で新人を守る研修・指導が不足。
2️⃣ 看護師教育の構造問題
制度疲労が志願者減少を招いている。教育現場と現場医療の乖離。
3️⃣ ツアーナースと学校教員の対立リスク
校長など決定権者との連携強化が必要。現場任せの体制に課題。

Q&A(よくある質問)
Q1. いじめが辛い…今すぐ転職すべき?
A. 「いつまで働くか」を日付で決め、記録(メモ)を残しつつ並行して情報収集。証拠保全→上長・産業保健→外部相談(労基・看護協会)→異動or転職の順で。逃げ続けるのではなく出口を自分で決めるがコツ。
👉 「辞める前に読んでおきたい後悔しない転職のヒントはこちら。」
👉 職場でのハラスメント対策や相談窓口については、
日本看護協会|働き方・ハラスメント防止 の情報も参考になります。
Q2. 10年のブランク。何から再開すれば?
A. 点滴・感染対策・認知症ケアの最新ガイドを1テーマずつ復習→復職支援研修/就労支援を活用→まずは時短・非常勤で感覚を戻すのが安心。
🩺 まずは情報収集から始めてみませんか?
復職支援に強い求人をまとめて比較 ▶︎ (看護roo! 公式)
👉 復職支援制度や研修情報は、
厚生労働省|看護職の復職支援 で確認できます。
Q3. 復職先は病院と介護施設どっちが合う?
A. 「治す(急性期)」志向なら病院、「暮らしに寄り添う」志向なら介護。夜勤可否、緊急対応耐性、家族都合(保育/介護)でマトリクス決め。
Q4. デイサービスの看護は新人には危険って本当?
A. 窒息/誤嚥など瞬発力が必要。急変対応に自信が付いてからがおすすめ。入るなら最初は同行・手順書整備・模擬訓練を条件に。

現場のベテラン看護師からの補足アドバイス
「それでも、どうしてもデイサービスで働いてみたい」という方へ。
経験値がまだ浅い段階であっても、
まずは特養などに併設されているデイサービス付き施設に在籍しながら、
少しずつデイサービス業務を見て学ぶ方法があります。
特養の看護業務を軸にしつつ、
「送迎・バイタル・レク前後の健康管理」などを部分的に経験することで、
安全にステップアップできます。
この方法なら、
✅ 施設全体のサポートが得られやすい
✅ 急変対応のバックアップ体制がある
✅ デイ勤務への移行判断がしやすい
と、守られながら学べる現実的なステップになります。
Q5. 面接で本当の現場を見抜く質問は?
A. 「直近3か月の退職理由」「直近のインシデントと再発防止」「1日の人員配置表」「教育フロー(初日〜30/60/90日)」の4点を具体で。
Q6. 祖父母や家族が同じ施設にいる場合の線引きは?
A. 生活者として公平が原則。担当固定を避け、チームで情報共有。感情が揺れたら交代を申し出るのもプロ。
Q7. 認知症ケアでイライラしないコツは?
A. 先回り(環境×時間×声かけ)で不穏を起きにくくする。自分のクールダウン手順を決めておく(深呼吸→席を外す→交代依頼)。
Q8. 給与より 続けられる職場 の見極めは?
A. ①残業の実測値(打刻)②有給取得率③教育担当の有無④人員配置の“穴”対応(欠員時の代替)——数値で確認。
Q9. ツアーナースで学校側とぶつかるのが不安…
A. 事前に校長・養護教諭と権限と連絡フローを文書化。緊急時は誰が最終判断か、保護者連絡タイミングまで決めておく。
Q10. 履歴書の空白期間はどう書く?
A. 事実+学び+再発防止/再現性。「家族介護:訪問看護・認知症ケアを体系的に学習→現場復帰後に○○へ活かす計画」など前向きに。
Q11. 派遣・単発からのリスタートはアリ?
A. スキルの棚卸と合う現場の試し履きに最適。雇用の安定性や教育の薄さはあるので、半年以内に常勤/非常勤へ軟着陸の計画を。
Q12. 夜勤がしんどい。辞める以外の選択肢は?
A. 固定日勤・準夜のみ・回数調整・回復期/外来/健診/在宅などへ配置転換。睡眠衛生(光・温度・カフェイン)も可視化して最適化。
Q13. 職場の人間関係が地雷かどうか、見学で分かる?
A. 挨拶の返礼率、申し送りのトーン、ナースステーションの掲示物(責める文言が多いか)、休憩室の雰囲気を観察。違和感はだいたい当たる。
Q14. 仕事と身内介護を両立したい
A. 介護保険の活用(通所/ショート/福祉用具)+職場と固定シフト合意。限界ライン(休む/調整する基準)を先に紙で共有。
Q15. 「逃げない」って、我慢とどう違う?
A. 我慢=自分を削る停滞。逃げない=現状に寄り添いながら変数(期限・役割・職場)を主体的に動かすこと。小さく動かすのがコツ。
👉 「今後の医療業界の将来性や、AI時代を生き抜くキャリア戦略はこちらの記事で解説しています。」
まとめ「変わるのは、自分」
いじめもブランクも、介護も乗り越えた彼女の口癖はこうです。

「逃げずに寄り添って、自分が変わる。」
完璧を求めるのではなく、折れない心を育てること。
それが、長く現場で働き続けるための「しなやかな強さ」です。
あなたの看護観は、どこにありますか?
彼女の経験から、その答えを見つけてみてください。