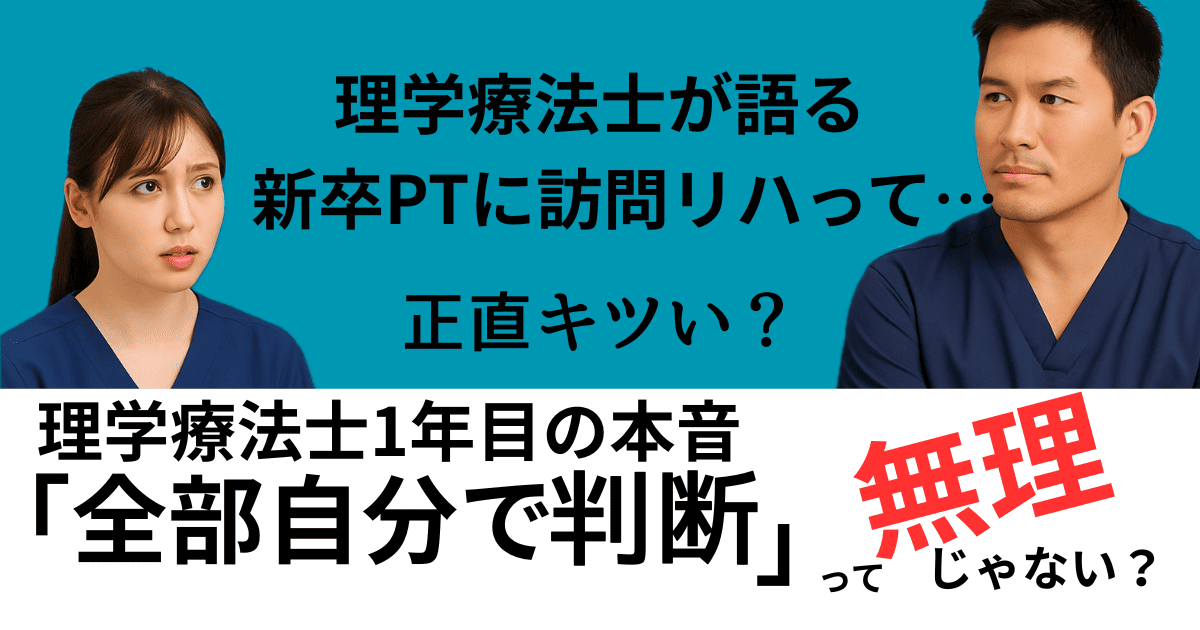※本記事にはPRを含みます
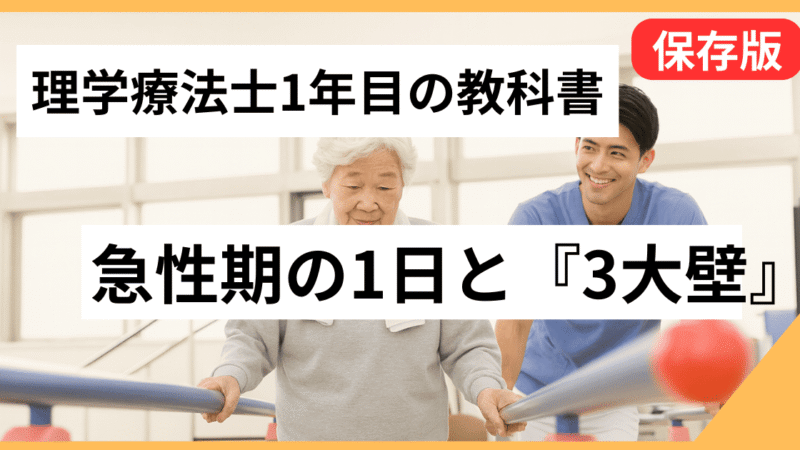
本記事は理学療法士の個人経験の共有であり、医療行為の指示ではありません。勤務上の判断は所属施設の手順・上長/主治医の指示に従ってください。数値・待遇は時期・地域・規模で変動します。
総合病院の現役PT(4年目)が、急性期1日の流れと新人がつまずく「技術・時間・メンタル」の越え方を等身大で解説。 SBAR30秒要約や7分で終わる記録テンプレなど、今日から使える“型”を配布。臨床推論の回し方、多職種連携、将来のフィールド選びまで一気に掴めます。
✅ 急性期PT1年目の1日は「申し送り→評価→介入→カンファ→記録」が基本
✅ 「きつい」3大壁=〈技術/時間/メンタル〉→ OJT同行・記録テンプレ・相談動線で突破
✅ 連携はSBARの30秒要約を型化。本文でテンプレ配布
この記事でわかること
- 急性期PT1年目の1日の流れ(タイムラインとコツ)
- 「技術・時間・メンタル」3大壁の対策
- 臨床推論の回し方と症例ノートの型
- SBAR30秒要約テンプレで多職種連携
- フィールド別の向き不向きと選び方
監修/事実確認済み
取材情報
👤 現役理学療法士(総合病院・4年目)
📅 取材:2025/08/18|最終更新:2025/08/20
🛡️ 編集:医療系インタビュー連載(体験談中心/事実確認実施)
訪問リハに興味がある方は下記の記事をチェックしてね⇩
プロフィールとキャリアのはじまり
高校野球の怪我がきっかけ|理学療法士を選んだ理由
結論:受け手から支える側へ——怪我で理学療法士に救われ、同じ体験を届けたいと思った。
高校最後の大会直前に負傷し、理学療法士の支援で復帰を目指した経験が進路の決め手でした。医療職とは無縁だった私が、**“回復のプロセスを設計する仕事”**に魅力を感じ、理学療法士の道を選びました。
参考: 公益社団法人日本理学療法士協会「理学療法士を知る」 (最終閲覧:2025/08/25)
総合病院を選んだ理由|半年ローテで適性を見つける
結論:幅広い症例×教育制度で“最短で適性を見極める”ため、総合病院を選択。
就職は900床規模の地域中核病院。決め手は6か月ごとのローテーション教育で、急性期/回復期/外来/訪問まで経験できること。配属が定まっていない1年目でも、症例数・指導体制・評価の基準が整っており、土台を作るのに最適でした。
ローテ期間・回数と、配属決定のルールは?
1年目のOJT体制(担当指導者/面談頻度)は?
1人あたりの1日の担当件数と記録システムは?
症例カンファの頻度と参加職種は?
評価項目の標準化(例:ROM/MMT/FIM)有無は?
勉強会・外部研修の費用補助は?
残業の実績中央値と記録の締め切りは?
配属希望の反映率と異動の目安は?
多職種連携の窓口(医師/看護/MSW)とSBAR文化は?
1年目の評価基準(到達目標)と昇給の根拠は?
はじめに:理学療法士1年目の「理想と現実」
国家試験に合格して憧れのPTになっても、現場のギャップに戸惑う瞬間はあります。この記事では、総合病院で働く現役PTが、1年目の1日の流れ・勉強法・多職種連携・将来像まで、等身大で語ります。新人PTや学生さんの不安軽減に役立つはずです。
1年目「1日の流れ」と仕事のルーティン
基本動線は〈申し送り→評価→介入→カンファ→記録〉
ここでは、私の病院リハビリ 1日の流れを具体的に紹介します。
- ⏰ 8:30 申し送り — 落とし穴:情報過多/対処:SBAR30秒
- 📝 9:00 評価・介入 — 落とし穴:項目ブレ/対処:ROM・MMT・FIM固定
- 👥 16:00 カンファ — 落とし穴:要件散漫/対処:目的1つ+次の一手
- 📋 17:00 記録 — 落とし穴:長文化/対処:7分テンプレ+定型文10
記録は、1症例あたり平均7分で終わるようにテンプレートを活用しています。事前に10個程度の定型文を登録しておくことで、入力を効率化できます。
1年目で“きつい”と感じた壁&乗り越え方
主訴:◯◯時に△△が困難。目標:○日後に××自立。
評価:ROM◯◯、MMT◯◯、Pain NRS◯/10、FIM◯◯。
介入:◯◯実施(目的/負荷/回数)。反応:○○改善。
考察:仮説A(◯◯)優位。次回:負荷+○○確認。
連携:看護へ◯◯共有、医師へSBARで◯◯提案済。
最大の壁:技術不足による結果の出なさ。痛みが改善せず先輩へ担当変更になる悔しさ。
乗り越えた行動
- OJT同行を即依頼(今日中/担当先輩:△△)
- 仮説メモをレビュー(明日朝カンファ前/評価→仮説→検証の順)
- 症例ノートを標準化(今週中に5症例を同フォーマット化)
スキルアップと理学療法士の勉強法
【相談動線】担当先輩 → 主任PT → 医師(SBAR30秒)→ 看護(転倒/疼痛)→ MSW(家族支援)
臨床に効く勉強法と情報収集
新人PTのうちは、覚えることが山積みです。私の場合は、まずは院内研修や勉強会に積極的に参加しています。
外部のセミナーも大切ですが、まずは身近な環境から学ぶことが効率的です。また、運動器エコーを学ぶために、有名な先生の病院に行って教わる機会もありました。
臨床推論の鍛え方
NG:「一度見てもらえますか?」
OK:「結論:歩行が軽介助へ悪化。根拠:MMT2+/5、離床量未達。提案:本日は座位耐久へ目標修正し午後OT併用、よろしいですか?」
臨床推論を鍛えるには、評価→仮説→検証のサイクルを常に意識することが重要です。困った症例は先輩に相談し、「なぜそう考えたか?」をレビューしてもらうことで、論理的な思考力が身につきます。
①1症例の記録≤7分 ②離床量/歩行距離↑ ③“当日相談”が1回以上
多職種連携のコツ(医師・看護・OT・ST・栄養・MSW)
【S】◯◯病棟の△△様、今朝から○○でADL低下。歩行は監視→軽介助に悪化。
【B】入院3日目、肺炎で抗菌薬投与中。発熱は解熱傾向、SpO2 94%(室内気)。
【A】起立時のふらつき増。筋力3/5→2+/5。離床量が予定未達。
【R】本日は座位耐久→短距離歩行に目標修正、午後にOT併用で再評価を提案。
- SBAR(状況/背景/評価/提案)で30秒要約
- 専門用語は患者目線に翻訳して共有
- 外科医の繁忙タイムは要件を1つに絞る+結論先出し
- 退院支援はADL+家屋状況+家族支援を箇条書きで提示
理学療法士のワークライフバランス|1年目のルーティンと筋トレ習慣
🎯睡眠≥7h/週3回・10分筋トレ/残業≤5h/趣味時間≥週2h
メンタル保全ミニ習慣(夜5分)
- 今日の“できたこと”を3つ
- 次回の“一手”を1つだけ書く
- 21時以降はチャット遮断(通知OFF)
理学療法士と筋トレ習慣
「理学療法士 ワークライフバランス」をどう保つか?これは多くの人が悩むテーマです。私は、仕事以外に夢中になれる時間を持つことが大切だと考えています。私の場合、それが週に3回の筋トレと、お菓子作りです。
理学療法士は体力仕事です。筋トレで体力をつけることはもちろん、良い姿勢や腰痛対策にもつながり、臨床にも良い影響があります。
体調や既往により適切性は異なります。無理のない範囲で。心配があれば産業医/主治医に相談を。
①今週できた3つ:
②溶けた時間の原因1つ:
③来週やめる/増やすを各1つ:
働き方の選択肢と将来像
将来性とキャリアプラン:どこが向いている?
- 急性期:変化が速く、医学的管理と連携力が鍛えられる
- 回復期:中長期でのゴール設計・家屋調整が学べる
- 外来/スポーツ:自立支援・セルフマネジメント重視
- 訪問:生活環境の評価力・家族支援
- 教育/研究/管理:臨床以外のスキルも活きる
著者の志向は外来リハへ。まずは臨床で幅を広げ、適性を事例で確認する方針。
理学療法士の転職基準と情報収集チェックリスト
転職を考える際、学び・人間関係・待遇・立地のバランスをどう取るか、自分なりの基準を持つことが重要です。特に給与面は、看護師など他の医療職と同様に課題として挙げられます。
5問でわかる“適性セルフチェック”
□ 変化が速い場で判断するのが好きだ(YES多→急性期/外来)
□ 中長期で目標を設計し関係性を築くのが得意(→回復期/訪問)
□ 一人で現場を回すより、場を仕組み化するのが好き(→教育/管理)
□ 生活環境・家族支援まで踏み込むのが苦にならない(→訪問)
□ 業務時間の予測可能性を重視する(→回復期/外来/教育)
・1年目~3年目の到達目標と評価方法は?
・担当件数/日と、記録の締め切りは?
・カンファの頻度と参加職種、SBAR運用の有無は?
・OJT/メンター体制(面談頻度/同行ルール)は?
・残業の実績中央値と、記録短縮の仕組みは?
・外部研修の補助(費用/勤務扱い)は?
よくある質問(FAQ)
Q1. PTに向いている人は?
A. **PDCAを楽しめる・安全第一で判断できる・他職種と短文で連携できる。**結果よりプロセス学習を積み重ねられる人。
Q2. 新人の壁はいつ超えた?
A. **一人で抱え込まない体制ができてから。**OJT同行+症例レビューを習慣化し、評価→仮説→検証のループが回り始めて徐々に。
Q3. 残業・休日・年収の体感は?
A. 残業は月約5時間。記録は時間内完了を意識。年収は昇給幅が小さめに感じることも(地域・規模差大)。
— 追加すると検索に強い —
Q4. 記録が遅い時の対処は?
A. 7分テンプレ+定型文10個に統一。主訴/所見/介入意図/反応/次の一手の順で短文化。
Q5. SBARは何秒?コツは?
A. 30秒。配分はS15秒・B10秒・A/R5秒。Yes/Noで返せる提案で締める。
まとめ
結論:〈評価→仮説→検証→共有〉を“型”で回し、OJT+振り返りで独学の遠回りを避ける。自分に合うフィールド×指導者を早めに見つける。
「明日やること」3つ
SBAR30秒を1回実施(Yes/Noで締める)
記録7分テンプレ+定型文を3つだけ登録
相談動線を紙に可視化(誰に/いつ/手段)
自分に合うフィールド×指導者を見つける
焦らず1歩ずつ。経験は必ず武器になります。